「地震対策」のお話し
昨今、地震への備えをされているご家庭も多いかと思いますが、
家を建てるときにも、必ず考えなければならないのがやはり、建物の地震への対策です。
政府の地震調査委員会は、今後30年以内に震度6弱以上の強い揺れに見舞われる確率を示した予測地図を公表しています。
では、実際に大地震が起きたとき、建物はどのような役割があり、どうあるべきでしょうか。
その安全性の目標として、次の3つの考え方があります。

① 人命を守る
建物の倒壊を防ぎ、家具の転倒や火災の発生を防ぐ。
② 財産・資産を守る
個人や企業が持つ財産・資産が地震で損なわれないようにする。
③ 生活機能を守る
生活や事業、社会的使命といった建物本来の役割を継続する。
こうした安全性を実現するために、現在はさまざまな耐震技術が活用されています。
代表的なのは、
揺れに耐える「耐震構造」
揺れを抑える「制震構造」
揺れを伝えない「免震構造」
の3種類です。
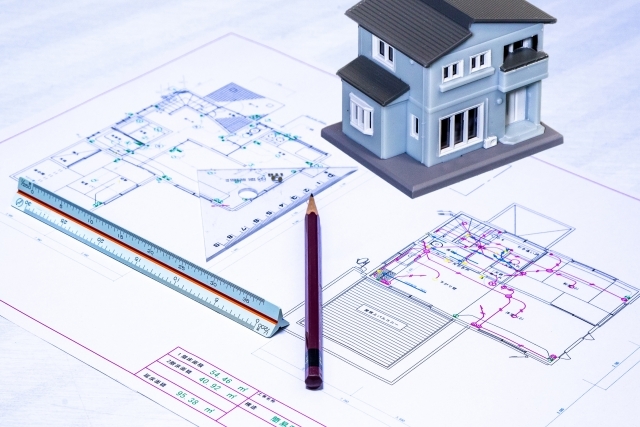
ここからは、それぞれの違いについてお伝えします。
制震構造
「制震」とは、建物にエネルギー吸収装置を組み込み、揺れを抑える工法です。
超高層ビルや橋にも採用される最新技術で、住宅にも応用されています。
ただし、地震の揺れ自体は建物に伝わるため、土地の条件によっては建ぺい率の制約により、設計に工夫が必要な場合もあります。
免震構造
「免震」は、建物の基礎部分に積層ゴムやベアリングを設置し、地面の揺れを建物に直接伝えない工法です。
住宅が地面から切り離されて浮いているような状態となり、地震対策としては非常に理想的です。
一方で、風の影響を受けやすいことや、コストが高くなる傾向があるといったデメリットもあります。
耐震構造
「耐震」は、筋交いや面材などを使って建物自体の強度を高め、揺れに耐える工法です。
建築基準法では、1923年の関東大震災クラスの地震に耐えられる建物を耐震等級1と定めています。
耐震等級1は現在の最低基準となっており、他には耐震等級2・耐震等級3があります。

以上が耐震・制震・免震構造の特徴です。
どの工法にもメリット・デメリットがあるため、「地域の特性」「建てたい家の条件」「予算」などを踏まえて選ぶことが大切です。
また、これらの工法は組み合わせて導入されることもあります。(例:耐震+免震、耐震+制震)
今回は「大切なものを守る技術」についてご紹介しました。
少しでも皆さまの家づくりの参考になれば幸いです。
伊丹市・宝塚市・川西市の注文住宅なら
木久工務店 久下正義
